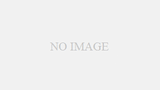「師走(しわす)」という言葉は、日本の旧暦で12月を指す月の名前です。
その起源にはいくつかの説があり、確定的なものではありませんが、代表的な説をいくつかご紹介します。
〇「師(僧侶)が走る」説
最も有名な説で、年末になると忙しくなる僧侶(師)が各家庭を訪れて読経や法要を行うために走り回るという意味です。
この説は、年末の忙しさを表現したものとして広く知られています。
〇「年果つ(としはつ)」説
「年が果てる」という意味の「年果つ(としはつ)」が転じて「しはつ」となり、さらに「師走」と表記されるようになったという説です。
年末を意味するシンプルな解釈です。
〇「四極(しはつ)」説
中国の暦法に由来する説で、12月を「四極」と呼んだことから、これが「師走」となったというものです。
「四極」は1年の終わり、つまり四方の極まりを意味します。
〇「為果つ(しはつ)」説
「物事を成し終える」という意味の「為果つ(しはつ)」が語源とする説です。
年末に一年の締めくくりをするという点で、この説も筋が通っています。
これらの説はいずれも12月が一年の終わりであり、忙しさや締めくくりを象徴していることを反映しています。
日本の暦や文化に根ざした美しい言葉と言えますね。
師走(しわす)は、1年の終わりを迎える12月であり、多くの人にとって忙しい時期ですが、同時に振り返りと新たなスタートを考える大切な時間でもあります。