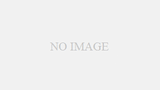除夜の鐘が108回鳴らされる理由は、仏教の教えに由来しています。
この数字には、人間が持つ「煩悩(ぼんのう)」の数が関係しています。
煩悩とは、私たちの心を悩ませたり、迷わせたりする欲望や執着のことです。
108の意味
仏教では、煩悩の数を108としています。この108は、以下のような計算に基づいています:
- 六根(ろっこん):人間の感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)
- 六境(ろっきょう):感覚器官が接する対象(色、声、香、味、触、法)
- 六識(ろくしき):感覚器官と対象が接触して生じる認識
これらが掛け合わさることで、6 × 6 × 3 = 108の煩悩が生じるとされています。また、他の説では、人間の1年の中での感情や執着を四季や月、方角などに関連付けて108とする考え方もあります。
除夜の鐘の意味
除夜の鐘を108回鳴らすのは、これらの煩悩を1つずつ取り除き、新しい年を清らかな心で迎えるためです。鐘の音が煩悩を洗い流す象徴とされ、年の終わりに心を整える重要な儀式となっています。
実際の鐘の数
お寺によっては、108回すべてを大晦日の夜に鳴らす場合もあれば、107回を大晦日に鳴らし、最後の1回を新年に鳴らす場合もあります。これは、旧年を締めくくり、新年を迎えるという意味合いが込められています。
鐘を鳴らし始める時間
除夜の鐘を鳴らし始める時間は、お寺や地域によって異なりますが、一般的には大晦日の夜11時半頃から始められることが多いです。以下の流れが一般的です:
1.107回を大晦日に鳴らす
旧年中の煩悩を清めるために107回を大晦日の夜に鳴らします。
2.最後の1回を新年に鳴らす
残りの1回は、新年を迎えた瞬間、つまり午前0時に鳴らされることが多いです。
これには、年をまたいで新しい年の清らかなスタートを切るという意味があります。
地域やお寺による違い
一部のお寺では、鐘を鳴らし始める時間や回数の配分が異なる場合もあります。
また、近隣への配慮から鐘の回数を減らしたり、参加者が鐘をつける体験型の行事にするなど、現代的な工夫がされている場合もあるようです。