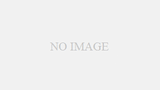成人式の由来
成人式は、日本の伝統的な儀式である「元服(げんぷく)」に起源を持ちます。
元服は奈良時代以降、数え年で12歳から16歳頃の男子が行った儀式で、髪型を子供のものから大人のものに変え、服装も改め、名前を変えたり冠をつけたりしました。
これは、社会的に一人前の大人として認められるための通過儀礼でした。
さらに遡ると、中国の通過儀礼である「冠礼(かんれい)」が起源とも言われています。
現代の成人式は、第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)に、埼玉県蕨市で開催された「青年祭」が発祥とされています。
戦後の混乱期、将来を担う若者を励ます目的で行われたこの催しが全国に広まり、1949年(昭和24年)には1月15日が「成人の日」として制定されました。
その後、祝日法の改正により、成人の日は1月第2月曜日となっています。
成人式は、若者が社会の一員として大人になったことを自覚し、責任を果たすことを誓う場です。
地域社会にとっても、若者の成長を祝い、地域の一員として迎え入れる大切な機会となっています。
成人式で女性が着る振袖は、未婚女性の第一礼装であり、華やかで美しい装いです。
振袖には様々な柄があり、健康や長寿、子孫繁栄などの意味が込められています。
2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、多くの自治体では成人式は従来通り20歳を対象に行っています。
これは、成人式が単なる法的成人の祝いではなく、地域社会における通過儀礼としての意味合いを強く持っているためです。
つまり、成人式は古い伝統と戦後の復興という二つの側面を持つ儀式であり、若者の成長と社会への参加を祝う大切な行事と言えるでしょう。